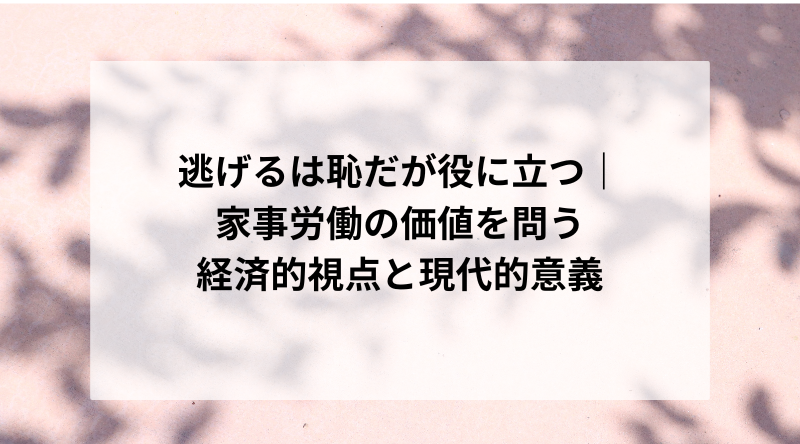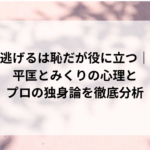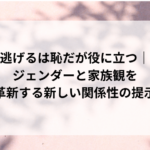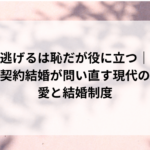「逃げるは恥だが役に立つ」が問う家事労働の価値|見えない労働を可視化する経済的視点
TBS系列で放送された「逃げるは恥だが役に立つ」(公式サイト:https://www.tbs.co.jp/NIGEHAJI_tbs/)が社会現象となった理由の一つに、家事労働を「仕事」として明確に位置づけた点があります。主人公の森山みくりが津崎平匡の家で働く際、彼女は家事を専門的な労働として捉え、時給換算で報酬を得る契約を結びます。この設定は、長年「無償の愛情労働」として扱われてきた家事の経済的価値を可視化し、多くの視聴者に家事労働について考える機会を提供しました。本記事では、ドラマが提示した家事労働の価値と、その背景にある経済的・社会的な視点について、詳しく考察していきます。
前回の記事はこちら 平匡とみくりの心理とプロの独身論を徹底分析
家事を「労働」として位置づける革新性
ドラマの中で、みくりは平匡の家で行う家事に対して、明確に報酬を求めます。掃除、洗濯、料理、買い物といった日常的な家事作業を、専門的なスキルを要する労働として捉え、その対価を時給で計算するのです。この発想は、従来の日本社会における家事の扱い方とは大きく異なります。
従来、家事は主に女性が担う「愛情労働」として認識されてきました。妻が夫のために料理を作り、家を掃除することは、愛情の表現であり、当然の義務とされてきました。しかし、この認識には大きな問題があります。家事が「愛情」という名目で無償化されることで、その経済的価値が見えなくなり、家事を担う人々の労働が正当に評価されないのです。みくりの選択は、この構造に対する静かな異議申し立てとも言えます。
ドラマでは、みくりが家事の時給を具体的に提示する場面が描かれます。この数字の設定自体が、家事労働には明確な経済的価値があることを示しています。料理の技術、掃除の効率性、時間管理能力――これらはすべて専門的なスキルであり、市場で評価されるべきものなのです。みくりの姿勢は、家事を「誰でもできる簡単なこと」とする偏見を否定し、家事こそが高度な専門性を要する労働であることを明確にしました。
契約という形式が可視化するもの
みくりと平匡の間で交わされる雇用契約は、家事労働の可視化という点で極めて重要な役割を果たします。契約書には、業務内容、労働時間、報酬、休日などが明記されており、通常の雇用契約と何ら変わりません。この形式化によって、家事が「なんとなく行われるもの」から「明確に定義された労働」へと転換されるのです。
特に注目すべきは、労働時間の設定です。みくりの業務時間は明確に定められており、それ以外の時間は彼女のプライベートな時間として保護されます。これは、通常の家庭では曖昧になりがちな「家事の境界線」を明確にする試みです。実際の家庭では、家事に「就業時間」という概念はなく、朝から晩まで、時には夜中でも必要に応じて家事が行われます。この無限定性が、家事労働者の負担を増大させる一因となっているのです。
また、契約には休日の規定も含まれています。みくりは週に一日の休日を持ち、その日は家事をしない権利が保障されます。この設定は、家事労働者にも休息が必要であることを示しています。通常の家庭では、主婦に「休日」という概念はなく、365日家事が続くことが当然視されてきました。ドラマはこの不条理に光を当て、家事労働者の権利について考えるきっかけを提供しているのです。
「業務報告会」という対話の場
みくりと平匡が定期的に開く「業務報告会」は、ドラマの重要な要素の一つです。この会議では、家事の実施状況、改善点、新しい提案などが話し合われます。一見すると堅苦しく見えるこの習慣は、実は非常に合理的で健全なコミュニケーションの形です。
通常の家庭では、家事について明示的に話し合う機会は多くありません。「言わなくてもわかるはず」という暗黙の了解に依存し、結果として不満が溜まったり、誤解が生じたりします。しかし、みくりと平匡は言語化を徹底します。何がうまくいっているのか、何が問題なのか、どう改善すべきか――これらを定期的に確認し合うことで、両者の認識のズレを最小限に抑えているのです。
この業務報告会は、家事労働の「見える化」にも貢献しています。平匡は、みくりが日々どのような作業を行っているのかを詳細に知ることになります。料理一つとっても、献立を考え、買い物をし、調理し、後片付けをするという一連のプロセスがあることを、平匡は理解していきます。この可視化によって、家事労働への理解と尊重が深まるのです。また、この会議形式は、雇用主と労働者という関係でありながら、対等な立場での対話を保証する仕組みでもあります。
家事の専門性と効率化への視点
ドラマは、家事が単純作業ではなく、高度な専門性を要する労働であることを繰り返し示します。みくりは、掃除の効率的な手順、栄養バランスを考えた献立作成、食材の保存方法、洗濯物の適切な扱いなど、様々な知識とスキルを駆使して家事をこなします。これらは長年の経験と学習によって獲得されたプロフェッショナルな技能なのです。
また、みくりは家事の効率化にも積極的に取り組みます。時間を無駄にしない動線の設計、適切な道具の選択、作業の優先順位づけなど、まるでビジネスにおける業務改善のような視点で家事を最適化していきます。この姿勢は、家事を「なんとなくやるもの」から「計画的に実行するもの」へと格上げしています。効率化によって生まれた時間は、みくりの自由時間として保護され、彼女の生活の質を向上させます。
平匡もまた、みくりから家事のスキルを学んでいきます。当初は家事が全くできなかった彼が、少しずつ基本的な技能を習得していく過程は、家事が「教えられ、学ばれるべき技能」であることを示しています。これは、「女性なら誰でも自然にできる」という性別役割分業の前提を覆すものです。家事は生まれつきの能力ではなく、習得すべきスキルであり、性別に関係なく誰もが学ぶことができるものなのです。
感情労働としての側面
家事労働には、物理的な作業だけでなく、「感情労働」の側面もあります。家族の好みを把握し、体調を気遣い、快適な環境を作り出す――これらは目に見えにくいですが、重要な労働です。ドラマでは、この感情労働の存在も丁寧に描かれています。
みくりは、平匡の好みの食事を覚え、彼が疲れている時には消化の良いものを用意し、季節の変わり目には体調を気遣う言葉をかけます。これらは契約書には明記されていない「サービス」ですが、家事労働の本質的な部分でもあります。相手のことを考え、先回りして配慮すること――この感情労働こそが、家事を単なる物理的作業以上のものにしているのです。
興味深いのは、当初は契約関係として始まった二人の間でも、この感情労働が自然に生まれてくることです。みくりは「業務外」であっても平匡を気遣うようになり、平匡もまたみくりのために何かしたいと思うようになります。この変化は、家事労働における感情的な側面が、報酬とは別の次元で存在することを示しています。感情労働は完全に数値化したり契約化したりできない部分であり、それがまた家事労働の複雑さを物語っているのです。
現代社会における家事労働の再評価
逃げ恥が放送された2016年は、日本社会において働き方改革や女性活躍推進が議論されていた時期でもあります。ドラマは、こうした社会的文脈の中で、家事労働の再評価を促す作品として機能しました。家事を正当に評価し、対価を支払うという発想は、多くの視聴者にとって新鮮であると同時に、深く考えさせられるものでした。
実際の社会では、共働き世帯が増加する一方で、家事の負担は依然として女性に偏っている現状があります。仕事と家事の二重負担に苦しむ女性は多く、この状況は「ワンオペ育児」という言葉にも表れています。逃げ恥は、この問題に対する一つの解決策を提示しているわけではありませんが、少なくとも家事労働の価値を認識することの重要性を示しました。
ドラマが提起した問いは、放送終了後も多くの人々の間で議論され続けています。家事を外注することの是非、夫婦間での家事分担のあり方、家事労働者の権利保護など、様々な観点から家事労働が見直されるきっかけとなりました。ドラマというエンターテインメントの形式を通じて、社会的な課題に光を当てたことは、逃げ恥の大きな功績の一つと言えるでしょう。
家事と愛情の関係性
ドラマが巧みなのは、家事を労働として位置づけながらも、家事と愛情の関係を否定していない点です。みくりは当初、純粋に仕事として家事を行っていますが、平匡への感情が芽生えるにつれて、家事の中に愛情が込められるようになります。この変化は、家事が報酬のためだけに行われるものではなく、相手への気持ちの表現にもなり得ることを示しています。
重要なのは、愛情があるからといって家事が無償になるべきではないという点です。愛情と報酬は対立するものではなく、両立し得るものです。愛する人のために料理を作ることと、その労働に対して正当な評価を受けることは、矛盾しません。むしろ、労働が正当に評価されることで、家事を担う人の自己肯定感が高まり、結果として関係性がより健全になる可能性すらあります。
ドラマの後半では、みくりと平匡の関係が深まるにつれて、契約という枠組みが徐々に形骸化していきます。二人は「雇用主と労働者」から「パートナー」へと関係性を移行させていきますが、それでも家事の価値が否定されることはありません。愛情が深まっても、家事の重要性は変わらず、むしろお互いに相手の労働を尊重し合う姿勢が強まっていくのです。この描写は、理想的なパートナーシップのあり方を示唆しています。
男性の家事参加と意識変革
ドラマは、平匡というキャラクターを通じて、男性の家事参加についても重要なメッセージを発信しています。当初、平匡は家事がほとんどできない人物として描かれます。彼は仕事では有能ですが、家事に関しては全くの素人です。これは、多くの日本人男性の現実を反映しています。
しかし、みくりと生活を共にする中で、平匡は徐々に家事のスキルを習得していきます。最初は簡単な掃除から始まり、やがて基本的な料理もできるようになります。この過程は、家事が「女性の仕事」ではなく、生活していく上で誰もが身につけるべき基本的なスキルであることを示しています。平匡の成長は、視聴者である男性たちに、家事参加への一歩を踏み出すきっかけを与えたかもしれません。
また、平匡がみくりの家事労働を尊重し、その価値を認める姿勢も重要です。彼は雇用主として、みくりの労働に対して正当な報酬を支払うだけでなく、その仕事の質の高さを認識し、感謝の言葉を伝えます。この態度は、家事を当然視せず、常に感謝と尊重の気持ちを持つことの大切さを教えてくれます。男性が家事労働の価値を理解し、家事を担う人に敬意を払うこと――これが、より平等で健全な家庭を作る第一歩なのです。
まとめ:家事労働の価値を見つめ直す
「逃げるは恥だが役に立つ」が提示した家事労働の経済的視点は、多くの人々に家事の価値を見つめ直す機会を提供しました。家事を「労働」として位置づけ、その対価を明確にすることで、長年見えなくされてきた家事の価値が可視化されたのです。
もちろん、すべての家庭で家事に報酬を支払うべきだと主張しているわけではありません。ドラマが示したのは、家事が高度な専門性を要する重要な労働であり、それを担う人々への尊重と感謝が不可欠だということです。報酬という形を取るか、言葉による感謝や家事の分担という形を取るかは、それぞれの家庭の選択ですが、いずれにしても家事の価値を認識することが出発点となります。
みくりと平匡の物語は、家事労働について考えるだけでなく、パートナーシップのあり方、対等な関係の築き方、コミュニケーションの重要性など、多くの示唆を与えてくれます。契約という形式を通じて可視化された家事労働の価値は、現代社会における家族のあり方、働き方、そして男女の関係性を問い直すきっかけとなりました。逃げ恥が社会現象となったのは、こうした深いメッセージが、コメディという親しみやすい形で多くの人々に届いたからなのです。