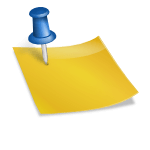『もしがく』が問う演劇の本質と人生という舞台
2025年10月1日からフジテレビ系「水曜10時枠」で放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(略称:もしがく)は、三谷幸喜が25年ぶりに民放ゴールデン・プライム帯の連続ドラマ脚本を務める話題作である。主演は菅田将暉、共演に二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波という豪華キャストが集結している。舞台は1984年の渋谷の架空の街「八分坂」で起こる青春群像劇であり、三谷が大学時代に渋谷の劇場でアルバイトをしていた実体験を元にした完全オリジナルストーリーとなっている。本作はシェイクスピアへのオマージュであり、タイトルは『お気に召すまま』の台詞「全てこの世は舞台、人は皆役者に過ぎぬ」(All the world’s a stage, and all the men and women merely players)の本歌取である。登場人物の名前や作中の店名などもシェイクスピア作品から取られており、作品全体がシェイクスピアへの愛に満ちている。本記事では、作品が持つ多層的なテーマ性と物語構造を分析していく。
こちらもチェック!
三谷幸喜の自伝的要素——大学時代の体験が生んだ物語
本作の最大の特徴は、三谷幸喜自身の体験がベースになっている点である。三谷は大学時代、渋谷の劇場でアルバイトをしていた。その時の経験、出会った人々、感じた葛藤や情熱——これらが本作の源泉となっている。主人公の久部三成(菅田将暉)は、蜷川幸雄に憧れる演出家の卵であり、劇団から追放されて路頭に迷う。この設定には、三谷自身の青春時代の苦悩が投影されている。また、作中には新人の放送作家・三谷幸平(生田斗真)というキャラクターが登場する。ジャケットにネクタイ姿の彼は、”三谷青年”がモチーフになっており、作品における三谷の分身とも言える存在である。この自伝的要素が、作品にリアリティと温かみを与えている。三谷は、自分の青春時代を美化するのではなく、その挫折や葛藤、そして小さな勝利を正直に描いている。
興味深いのは、三谷が脚本を2022年から執筆し始め、2025年春の撮影開始時には既に後半部分まで仕上がっていたという点である。遅筆で知られる三谷が、撮影前に脚本を書き終えるのは初めてのことだという。この異例の早さは、本作への三谷の情熱を物語っている。自分の青春時代を描くという個人的な動機が、創作意欲を高めたのだろう。また、撮影中には各俳優のキャラクターに合わせて書き直すなどの調整も行われた。これは三谷作品の特徴であり、俳優との協働によって作品を作り上げていく姿勢が見られる。本作は、三谷幸喜という脚本家の原点に立ち返る作品であり、彼がなぜ演劇に魅了され、脚本家になったのかという問いへの答えでもある。観客は、三谷の青春を追体験することで、演劇という芸術形式の魅力を再発見する。
シェイクスピアへのオマージュ——古典と現代の融合
本作のもう一つの核となるのが、シェイクスピアへのオマージュである。タイトルの「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」は、シェイクスピアの『お気に召すまま』(As You Like It)の有名な台詞「全てこの世は舞台、人は皆役者に過ぎぬ」(All the world’s a stage, and all the men and women merely players)を下敷きにしている。この台詞は、人生を舞台に喩えた哲学的な言葉であり、人間は皆、人生という舞台で役を演じているという世界観を示している。三谷は、このメタファーをさらに深め、「もし人生が舞台なら、楽屋(バックステージ)はどこにあるのか」という問いを投げかける。楽屋とは、役者が素に戻る場所、仮面を外す場所である。人生という舞台において、私たちは常に何らかの役割を演じているが、本当の自分でいられる場所(楽屋)はどこにあるのか——この哲学的な問いが、作品全体に通底している。
また、登場人物の名前もシェイクスピア作品から取られている。例えば、久部三成という名前は、『ハムレット』の久米川王子(Hamlet, Prince of Denmark)を連想させる。他の登場人物の名前や、作中に登場する店名なども、シェイクスピアの戯曲から引用されている。この細かいオマージュが、作品に知的な遊び心を与えている。シェイクスピアに詳しい観客は、これらの参照を発見する楽しみがあり、そうでない観客も、作品の背後にある古典への敬意を感じ取ることができる。シェイクスピアは、400年以上前の劇作家だが、その作品が描く人間性の普遍的なテーマは、今も色褪せない。愛、嫉妬、野心、裏切り、友情——これらのテーマは、1984年の渋谷を舞台にした本作にも共通している。三谷は、シェイクスピアの精神を受け継ぎながら、現代日本の若者たちの物語を紡いでいる。古典と現代の融合が、本作の大きな魅力となっている。
1984年の渋谷——巨大セットで再現されたあの時代
本作の舞台は、1984年の渋谷である。この時代設定には重要な意味がある。1984年は、昭和59年であり、バブル経済の前夜、日本がまだエネルギーに満ちていた時代である。渋谷は、若者文化の中心地であり、小劇場ブームが巻き起こっていた。つかこうへい、野田秀樹、鴻上尚史など、後に日本演劇界を代表する演出家たちが、この時代に頭角を現した。三谷幸喜自身も、この時代に大学生として演劇に触れ、その魅力に取り憑かれた。本作は、この熱気に満ちた時代への郷愁と、その時代を生きた若者たちへのオマージュである。しかし、1984年の渋谷を再現することは容易ではない。当時の建造物の多くは既に存在せず、渋谷の繁華街で長時間ロケをすることも困難である。そこで、制作陣は千葉県茂原市に巨大オープンセットを建設した。
三谷によると、このセットは当時の建造物そのままの配置で再現されており、俳優陣もセットのおかげで演技に集中することができたという。架空の街「八分坂」——渋谷駅から8分でたどり着くという設定のこのアーケード街は、ストリップ小屋のネオンが光る怪しい雰囲気を持つ。この街には、小劇場、喫茶店、バー、神社など、様々な場所があり、登場人物たちの人生が交錯する舞台となる。巨大セットの構築は、膨大な予算と労力を要したはずだが、その投資は作品のクオリティに直結している。俳優たちは、実際の街を歩くように演技でき、カメラは自由にその空間を捉えることができる。この物理的なリアリティが、作品に説得力を与えている。また、1984年という時代設定は、スマートフォンもインターネットもない時代であり、人々の繋がりが直接的だった時代を描くことを可能にしている。この時代だからこそ、演劇という「生の芸術」が持つ力が、より鮮明に描かれるのである。
演劇の本質を問う——なぜ人は舞台に立つのか
本作が最も深く問いかけるのは、「なぜ人は演劇をするのか」という根源的な問いである。久部三成(菅田将暉)は、蜷川幸雄に憧れ、理想のシェイクスピア劇を作ろうと奮闘する。しかし、彼の横暴ぶりに劇団員は反発し、彼は追放される。演劇に対する情熱と、それを実現するための手段——この両者のバランスが、久部の課題である。彼は、芸術のためなら何をしても許されると考えているが、演劇は一人では成立しない。役者、スタッフ、観客——全ての人々の協力があって初めて、舞台は完成する。この協働の難しさと美しさが、本作の重要なテーマである。また、作中には様々な立場で演劇に関わる人々が登場する。役者、演出家、照明スタッフ、劇場の支配人——それぞれが異なる動機で演劇に関わっている。成功を夢見る者、純粋に演劇が好きな者、生活のために働く者——多様な人々が集まることで、舞台は成立する。
演劇の本質は、「生の芸術」であることだ。映画やテレビと違い、舞台は毎回違う。同じ台本、同じ役者でも、その日の観客、その日の空気によって、舞台は変わる。この一回性が、演劇の魅力であり、同時に恐怖でもある。失敗は取り返しがつかない。しかし、その緊張感の中で生まれる瞬間の輝きが、演劇にしかない感動を生む。本作は、この演劇の本質を丁寧に描いている。久部が追求する「理想のシェイクスピア劇」とは何か——それは、完璧な技術ではなく、観客の心を動かす何かである。三谷幸喜は、自身の演劇経験を通じて、この本質を知っている。そして、その本質を視聴者に伝えようとしている。『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、演劇を愛するすべての人々へのラブレターであり、同時に、人生を生きるすべての人々へのメッセージでもある。私たちは皆、人生という舞台で役を演じている。その舞台を、どう生きるか——この問いが、作品の核心なのである。
まとめ
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、三谷幸喜の自伝的要素、シェイクスピアへのオマージュ、1984年の渋谷を再現した巨大セット、そして演劇の本質を問う哲学的テーマが融合した作品である。三谷が25年ぶりに民放連ドラ脚本を務めた本作は、彼の演劇への愛と、青春への郷愁が詰まった傑作となっている。菅田将暉をはじめとする豪華キャストの演技、YOASOBIの主題歌「劇上」も話題となり、2025年秋ドラマの注目作として高い評価を得ている。